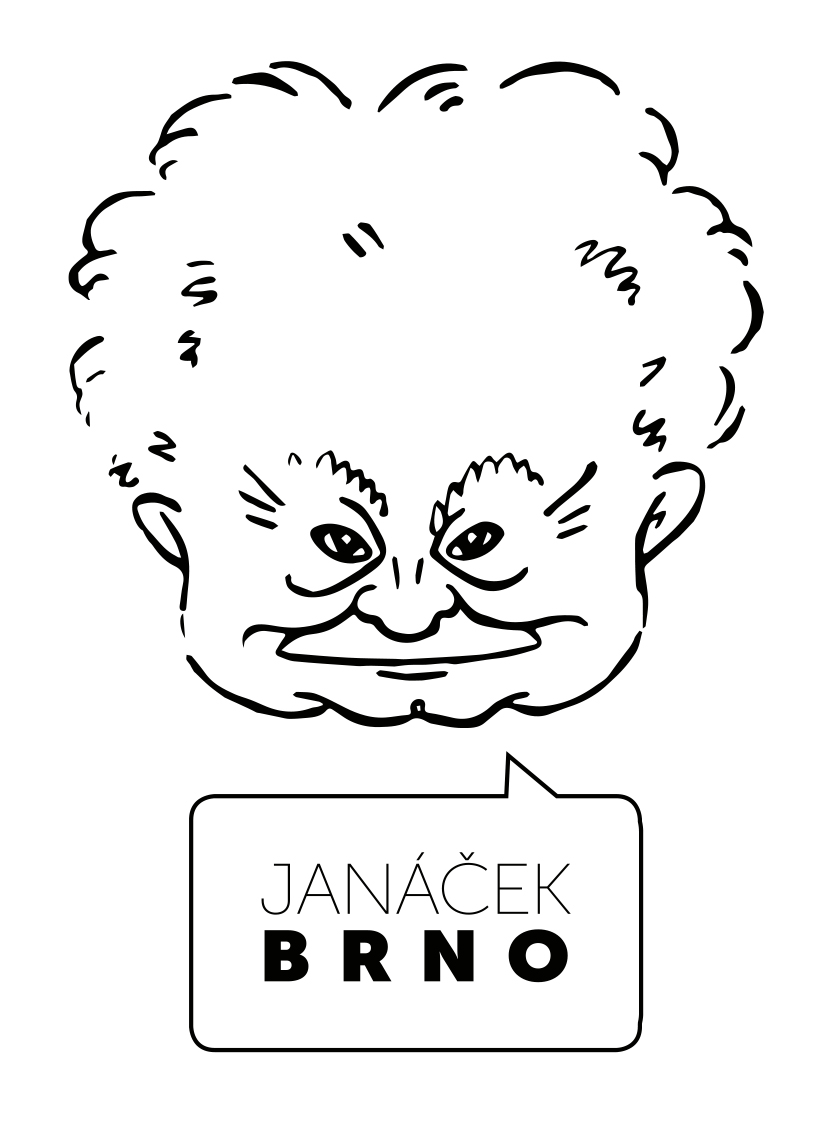ヤナーチェクの暮らしの様子
- 仕事と生活
- 家族
- 住まい
- 国外滞在
- 経済状況
仕事と生活
1928年ルジャンキ公園を散歩中のレオシュ・ヤナーチェク©モラヴィア博物館

ヤナーチェクの日々の生活ルーティーン、決まり事、習慣はある程度その時々抱えている仕事に左右されていました。1904年にブルノ師範学校を退職してから、作曲に時間を費やすことができるようになりました。その後はオルガン学校と作曲「のみ」に没頭しました。依頼されての作曲というケースはなかったので、作曲に追われることはなく、「物質的・心理的理由」が発生したとき作曲に励みました。例えば、スメタノヴァ通りにあるオルガン学校中庭に建てられた小さな家に引っ越した1910年頃のヤナーチェクのある1日は次のようでした。
夏は朝6時に、冬は朝7時に起床。ルジャンキ公園で散歩ののち朝食(愛犬チペラと一緒に)。質素な朝食に、たいていコーヒーを飲んだ。その後お昼まで授業、少し休憩して作曲。午後遅くに庭で新聞を読み、ブルノで散歩。早めの夕飯をとり、コンサートや舞台に行かないときは早めに就寝。次第に夜を仕事場の学校で過ごすようになり、よく夜通し作曲して朝方床に就くようになっていった(オズヴァルド・フルブナJaký byl Janáček、モラヴィア博物館ヤナーチェク・アーカイブ収蔵)。
家族
レオシュ・ヤナーチェクは11歳の時、自身のフクヴァルディの生家を出ました。子供時代からすでに家族との交流はありませんでした。故に大人になり必死で家族の居場所を探しました。そしてそれを、自身の上司であり師範学校校長エミリアン・シュルツの家庭に見出しました。彼の娘ズデンカに恋をし、1881年妻として迎えました。しかしズデンカとヤナーチェクの育った環境はあまりに異なり、ズデンカは両親に依存していて、このことが新婚の夫婦の間に頻繁に軋轢をもたらし、娘オルガの誕生後関係は一気に悪化しました。ズデンカは両親のもとへ戻り、一時は夫婦間の連絡も絶え、離婚の危機を迎えました。しかしながら離婚は何とか回避され、次第にレオシュとズデンカは和解していきましたが、夫婦の生活は幸せと言えるものではありませんでした。当時2歳だった第2子ヴラディミールの死もヤナーチェクは部分的にズデンカのせいだと考えていました。ヤナーチェクはもう一人子供が欲しいと願っていましたが、ズデンカがこれを拒否したことも関係悪化につながりました。聡明で美しい娘のオルガが何とか2人の仲を取り持っていました。オルガがたった21歳でこの世を去ってしまうと、ヤナーチェク夫妻の関係はますます冷えていきました。ズデンカはヤナーチェクがほかの女性に恋い焦がれる(プラトニックな関係であっても)のを許容せず、2人の共同生活は非常に緊張したものだった時期もありました。ヤナーチェクはこうした状況を離婚によって解決しようとしましたが、ズデンカはそれには応じませんでした。のちに夫婦は、法的拘束力はないものの、お互いの自由についての契約書を交わしましたが、状況改善には至りませんでした。様々な問題はあったものの、ヤナーチェク夫妻はヤナーチェクが亡くなるまで添い遂げました。
親愛なるズデンカ!
…シュテスロヴァーは私にラグと彼女と彼女の子供たちと私が映っている写真を送って来た。これを君に話したら、僕は君のものだってわかってくれると信じている。作曲家でいるということは燃える火のそばにいるようなものなのだ。フォエルステル、ノヴァーク―彼らは冷えたかまどのそばに座っている。もうそういうことになっているし、君となら大丈夫そうだ。
健康であることを願う!
君のレオシュより
妻ズデンカに宛てたレオシュ・ヤナーチェの手紙より (1928年1月26日)
住まい
レオシュ・ヤナーチェクは作曲活動を活発におこなった日々をブルノで過ごし、引っ越しを経験したのは一度だけでした。1910年にスタレー・ブルノのアパートから、スメタノヴァ通りにあるオルガン学校中庭に建てられた小さな家に引っ越しました。若い時は下宿生活も何回か経験しました。1882年からは妻のズデンカ、娘のオルガ、そして使用人のマリエ・ステイスカロヴァーと、修道院広場(現在のメンデル広場)2番の中庭に面したアパートに住んでいました。ヤナーチェクが30年間暮らしたこの家で第2子ヴラディミールが誕生し、のちにヴラディミール、オルガとも亡くなりました(ヴラディミール享年2歳、オルガ享年21歳)。
使用人マリエ・ステイスカロヴァーによる修道院広場のアパート回想録はこちらをご覧ください。

オルガン学校中庭に建てられた小さな家に引っ越した後は、夫婦の関係は改善されました。
使用人マリエ・ステイスカロヴァーによるスメタノヴァ通りの家の回想録はこちらをご覧ください。

国外滞在
ヤナーチェクは11歳の時からブルノをベースとし、ブルノから仕事や休暇のため様々な場所を訪れました。最初は定期的に仕事のためプラハに通っていました。50代を超えてからは夏のほとんどをルハチョヴィツェの温泉地で過ごし、カルロヴィ・ヴァリやボフダネチュ、ツリクヴェニツァ(現在のクロアチア)でも過ごしました。1890年代からは、最初は特に夏、その後は年間通して出身地のフクヴァルディを訪れるようになりました。スロヴァキアのシュトゥルブスケー・プレソも好んで訪れました。国外に行くことはあまりありませんでした。例外は留学で赴いたライプツィヒとウィーン、弟フランティシェクを訪ねて3回行ったロシア、出張で行ったバイエルン地方のエッティンゲンとワルシャワでした。チェコスロヴァキア共和国建国後からは、自身の作品を引っ提げて1923年ザルツブルク、1925年ヴェネチア、そして1927年フランクフルトで現代音楽協会(ISCM)の国際フェスティバルに参加しました。自身の作品のドイツでのプロデュースにも参加しました。1926年には、音楽評論家、作家でありヤナーチェクをかっていたローザ・ニューマーチ夫人の招待を受けてイギリスを訪れました。


1925年プラハで行われた現代音楽協会国際フェスティバル参加者とザーヴィストへの船での観光の様子©国立映画アーカイブ
経済状況
ヤナーチェク家の辻馬車料金メモ©JZアーカイブ

ヤナーチェクの経済状況は人生を通して様々でした。少年時代は貧しく、ブルノの修道院付属学校へは叔父であるヤン・ヤナーチェクの援助を得て進学しました。教師として師範学校で働き始めた1876年から1903年(健康のため休暇を取ることが認められ、その1年後年金生活を開始した)までは収入は安定しており、さらに少々の作曲で得られる収入もありました。1904年から1914年にかけては彼の経済状況はさらに良くなりました。高額の国民年金とオルガン学校からの給料を得ていました。この時も作曲活動よりは教職から得られる収入が大部分を占めていました。その後1916年プラハで、1918年ウィーンで「イェヌーファ」初演を経て、著作権料と公演料によってヤナーチェクの経済状況はますます豊かになりました。ウィーンの出版社ユニバーサル・エディションと契約を結び、さらに収入は増えました。1918年には作曲活動から得られる収入は、ヤナーチェクの全収入の2/3にも達しました。
1920年代も経済状況は引き続き好転していきました。プラハ音楽院の教授としての高収入、年金に加えて作曲活動や国からの賞の授与もあり、高齢のヤナーチェクは経済的に豊かになりました。しかしながら彼の生活レベルは以前とはそれほど変わりのないものでした。唯一の出費は、出生地フクヴァルディへの寄付やフクヴァルディでの動産および不動産購入によるものでした。
執筆:イジー・ザフラートカ「偉大なチェコの作曲家たち」(国立博物館、2020年)より抜粋。