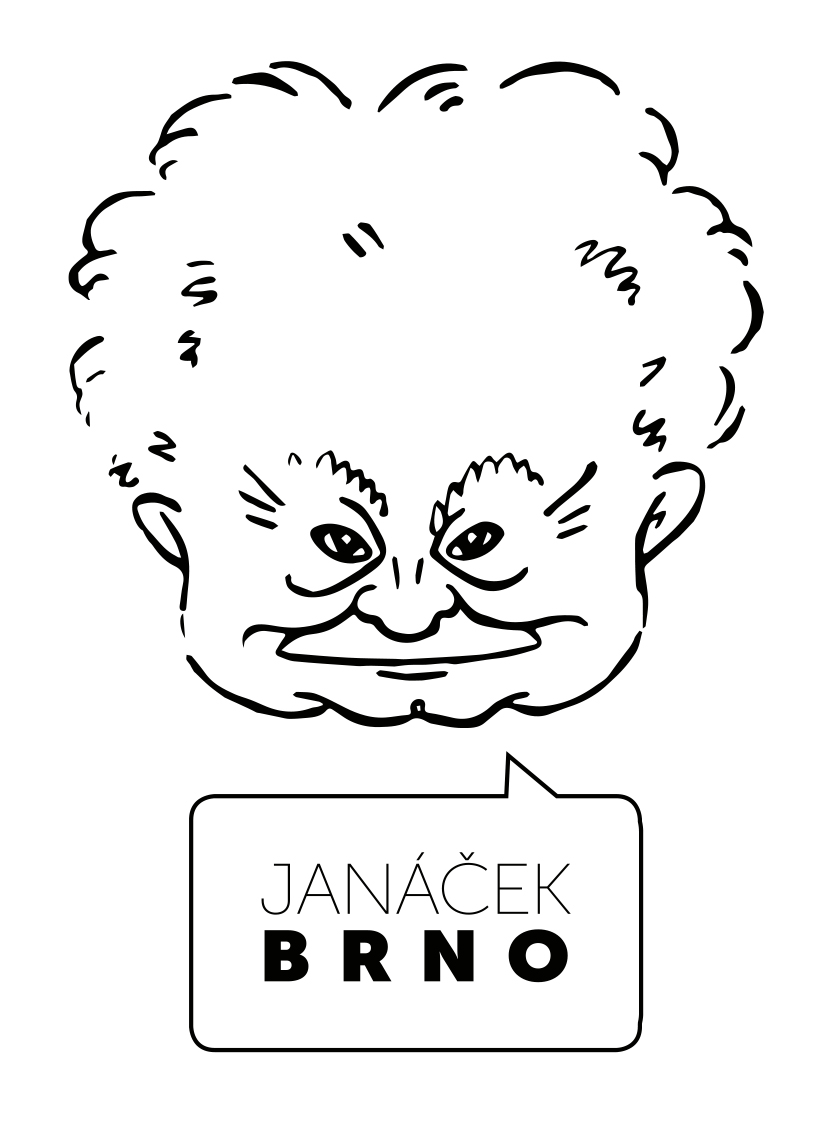ヤナーチェクの作曲・研究
- インスピレーション
- スピーチ・メロディ
- 創作過程
インスピレーション
ヤナーチェクの音楽の語法は、広義での彼の考えと切っても切り離せず、彼の視点や価値観を直接的に表しているので、インスピレーションというコンセプトは、ヤナーチェクの場合何か少し誤解を与えるものだと言えるでしょう。その中でも彼の作曲活動において基本的な意味を持つ点をいくつか挙げてみましょう。
1906年ストラーニーにてレオシュ・ヤナーチェクと「モラヴィアおよびシレジア民謡」実行委員会のメンバーたち©モラヴィア博物館

ヤナーチェクより一世代若いベーラ・バルトークと同じように、ヤナーチェクも自身の音楽の根幹を、自身で収集し学んだ民俗音楽と結びつけました。1888年頃からこういった傾向が見られ、それは亡くなるまで続きました。ヤナーチェクは民謡と民俗舞踊収集の第一人者で科学アカデミーとも協力し、モラヴィアおよびシレジア民謡実行委員会の委員長を務め、オーストリアのプロジェクトDas Volkslied in Österreichにも参加しました。民謡は記録しただけでなく、蓄音機に録音もしました。いくつかの全集の共著者であり、中でも有名なのは1901年にフランティシェク・バルトシュと出版した「新版モラヴィア民謡」です。民謡がヤナーチェクの作曲活動に影響を及ぼしたのは特に最初の方で、対話作曲、様式化、作曲された歌への導入部分などに見て取れます。例えば、「ヴァラシュスコ舞曲」、バレエ「ラーコシュ・ラーコツィ」の踊りの部分、オペラ「物語の始まり」や「モラヴィアの歌」などが挙げられます。1890年代後半からはこういった様式からは少し離れるようになりますが、彼の新たに生み出されていった音楽の語法の根幹にはずっと民俗音楽がありました。
ヤナーチェクにとってまたロシア文化との関係も大切なものでした。それはドイツ人がマジョリティであった当時のブルノにおける、チェコ人知識階層の汎スラブ主義的傾向によるものでした。1869年、聖キリル没後1000年記念祭で音楽行事に参加したヤナーチェクは、当時14歳でスラブ主義に傾倒し、叔父であるヤン・ヤナーチェクから「ロシアのキャンバス」のスラブの衣装を手に入れて、大きな祭典が始まるのを待ち構えていました。ロシア文化とロシア語との親密な関係から「新ロシア派」への変わり様は1870年代前半に見られます。若いレオは自分の名前に似たレフという名を用い、1873年ごろからロシア語とロシア文学への興味も抱くようになりました。1876年にブルノ・ベセダ合唱団のコンサートマスターになった頃、レールモントフの詩「死」をもとにメロドラマを作曲しました。スラブ主義傾向の強かったアントニン・ドヴォジャークとも親交を持ち、ピアニスト、アントン・ルビンシュタインに熱を上げ、彼のもとで学びたいと考えていました。チャイコフスキーにも熱を上げていました。彼の新ロシア派ぶりは子供たちの名前(オルガとヴラディミール)からも見て取れます。ロシアへの興味は、彼の弟フランティシェクがサンクトペテルブルクへ移住したことによって、ますます深まりました。フランティシェクとはその後ロシア語で文通し、彼を訪ねて3回ロシアを訪問しました。女性教育グループ「ヴェスナ」とも親しい関係があり、新ロシア派のヴェスナ所長フランティシェク・マレシュのおかげでロシア文学を購入したり、ヴェスナでロシア語のクラスも開講したりしました。
親愛なる弟よ!この手紙を手にしてお前は驚くだろう!私の友である所長マレシュはお前を訪ねて来たかね?マレシュにお前の住所を教えた。Пушкиновоюの祝いは大成功のうちに終わった。宜しく伝えておくれ。
Леошъ
レオシュ
弟フランティシェクに宛てサンクトペテルブルクに送った手紙より (1899年6月9日)
チェコ人エリート層と深いつながりのあったヴェスナとの関係は、1898年にロシア・サークルを生み出しました。発起人はもちろんレオシュ・ヤナーチェクです。彼はサークルの様々な役職を担い、1909年から1915年にかけてはサークル長になりました。主な活動は「文法練習、朗読、歌唱、新聞、雑誌、図書館、メンバーの集まり、(お茶を飲む)楽しい夜会、文法とロシア文学の講義、関連書籍と学習用資料の発行」を通してのロシア語の授業でした。もちろん「政治に関する話はしない」というのがルールでした。ヤナーチェクはサークルで楽しく活動し、ロシア語コースの世話をし、講義のための講師をアレンジしたりしました。15年間のサークル活動を経てロシア文学から作曲へのインスピレーションも得ました。1908年のトルストイのクロイツェル・ソナタをもとにした「ピアノ三重奏曲」およびのちの1923年に改作した「弦楽四重奏曲第1番」、1910年から1913年のジュコフスキーの「皇帝ベレンデイの物語」をもとにしたチェロとピアノのための「おとぎ話」、1915年から1918年のゴーゴリの同名小説をもとにした狂詩曲「タラス・ブルバ」などが例として挙げられます。そののちの1920年のオストロフスキーの戯曲「嵐」をもとにしたオペラ「カーチャ・カバノヴァー」や、ドストエフスキーの「死の家の記録」をもとにしたオペラ「死の家から」などは、新ロシア派としてよりは作品そのものへの興味が動機となって書き上げましたが、戦後ヤナーチェクのロシアに対する熱は少しずつ冷めていきました。ロシア文学はヤナーチェクの作曲活動において、プロットだけでなく登場人物のキャラクターや心理設定にも影響を与えました。


ヤナーチェクにとってまた、社会的側面と彼の秀でた共感力も大切な要素でした。社会的な不公平さに胸を痛め、1906年から1912年のペトル・ベズルチュの詩をもとに作った、表現主義の特徴も持ち合わせている合唱曲など、思いを込めた作品で応じました。
これらは全て、どちらかと言うとヤナーチェクの考え方そして作品に影響を及ぼすきっかけでした。アーティストとしてのヤナーチェクに必要であった、本当のインスピレーションのもと、感情的認識のきっかけは女性たちでした。ヤナーチェクが恋をしている時期は、作曲にも集中でき作品は短期間で完成しました。もちろんほかの要素も作品の完成までの期間に影響を及ぼすので、完全にそうと言い切ることはできませんが、ヤナーチェクが恋をしていない時は完成までに長くかかりました。実際に「イェヌーファ」は完成までに8年、「ブロウチェク氏の月への旅行」は9年かかりました。一方で、歌手でプラハ公演の際のコステルニチュカ役ガブリエラ・ホルヴァートヴァーに恋していた時期に作った「ブロウチェク氏の15世紀への旅行」はたった9か月で書き上げました。同じくらいの期間で、オペラ「運命」も書き上げました。この時は20歳年下のカミラ・ウルヴァールコヴァに惹かれていました。そんな中、ヤナーチェクの人生において最も大切な女性(妻ズデンカを除く)は、カミラ・シュテスロヴァーでした。明るく気難しさのない、28歳年下のカミラは、1917年からヤナーチェクにとって崇拝の的、恋人でした。彼女がいたからこそ、年を取ってからのヤナーチェクは次々と作品を生み出すことができました。彼女がいなければ「カーチャ・カバノヴァー」や「消えた男の日記」、弦楽四重奏曲「ないしょの手紙」はこの世に存在していなかったでしょう。




スピーチ・メロディ
ロシア文学愛好家としてヤナーチェクは、本質的に身近であった現実主義の立場をとっていました。人々の話し言葉を研究する際にもこの原理を貫きました。1897年から亡くなるまで、スピーチ・メロディと言われた、様々な場面における口語を楽譜として抽出する作業を続けました。30年以上もの間に、通りで、市場で、電車で、公園で、人々の集まりで、数千もの記録を行いました。スピーチ・メロディを彼は「人々の魂を覗く窓」と捉え、また「発せられた言葉の一つ一つに人生が乗っかっている」とも言っていました。
心理学の現代的な流れを汲んだ研究とも関連した人々の話し言葉の研究は、ヤナーチェクの作曲活動に、人々の心情、状況、そしてその表れという観点において重要な知識をもたらしました。ヤナーチェクにとってのインスピレーションは、彼が発話表現を通して研究した、考えを持ち喜びや悲しみという感情を持つ人間・かけがえのない個人であると言えるでしょう。ヤナーチェクはスピーチ・メロディそのものを直接作品に取り入れることはしませんでしたが、この研究によって音楽作品中にごく自然なキャラクターを描くことに成功しました。それは真実味を帯びており、よって彼の音楽の語法が私たちにとって親近感の湧くもので理解しうるものであると言えるのでしょう。小さな子供たちの片言(フクヴァルディでよく滞在していたスラーデック家の子供たちのお喋りをよく記録していた)、有名人のスピーチ、通りで、市場で、電車で、公園での通行人の話し言葉などの表れ方に興味を持ち、鳥類を中心に動物の鳴き声や、波の音、教会の鐘、嵐、床のきしむ音など、物や自然が織りなす音も記録していました。動物たちの表現を音として描いたものには、ピアノ曲集「草かげの小径にて」の「ふくろうは飛び去らなかった」や「利口な女狐の物語」の楽譜などがあります。

ヤナーチェクのスピーチ・メロディの記録は数千にものぼり、大部分は楽譜のみならず、対象物の情報とその時の状況(日付、場所、年齢、社会的立場、状況説明、心理的状況、出来事の説明)も記録されていました。ヤナーチェクはこれを大真面目な科学的な方法と捉えており、単語の長さなど、時間幅を正確に測れるヒップのクロノスコープを、科学アカデミーを通して用意しました。また、マサリク大学にスピーチ・メロディ研究を行う学科を作ることを条件に大きな成果を上げることを大学に遺言として残しましたが、実現はしませんでした。現代の視点からすれば、特にスピーチ・メロディの記録という観点から、そして楽譜としての記録というヤナーチェクの方法及び考え方は特異なものでしたが、科学的に客観的ではありませんでした。
スピーチ・メロディ?私にとって楽器や文学から奏でられる音楽、それがベートーヴェンであっても何でも、あまり真実味がない。それはいささか奇妙だった―誰かが私に話しかけてきて、私はその人が何を言っているかわからない、でもそのトーンの抑揚と言ったら!すぐにそれが何なのかわかった。その人がどのように感じ、嘘をついているのか、怒っているのか私にはわかった。誰かが私と話して、それが紋切り型の会話でも、その人は心の中で泣いているように聞こえたと感じた。トーン、人々の話し言葉や生きているものの発するトーンの抑揚は私にとってより深い真実を表している。ご存知だろうか。それは私の人生に必要なものだった。スピーチ・メロディは89年から収集している。かなりの数の記録がある。ドラマティックな音楽にとってスピーチ・メロディは大きな意味があると強調したい。
雑誌「Literární svět」のインタビューより(1928年)
スピーチ・メロディのオンライン・データベースはこちらからご覧ください。
ブルノの通りやフクヴァルディの森、電車の中でヤナーチェクが記録したスピーチ・メロディとはどんなものなのでしょうか?こちらをご覧いただくか、プレイリストを参照ください。
アメリカの作曲家・ピアニスト・YoutuberであるNahre Solによるヤナーチェクのスピーチ・メロディと日常の話し言葉の記録について、こちらのビデオをご覧ください。
創作過程

ヤナーチェクの作曲過程は基本的にはあまり変化しませんでしたが、成功を収める作品が増えるにつれて、一つの作品のコピーをいくつも作る必要性が出てきました。当初は作曲に五線紙を使っていましたが、年を重ねるにつれて普通の紙にラスターという道具(譜表の5本の線を平行に引くための道具)で自ら線を書いて使いました。万年筆と黒いインクを用いていました。
作曲に取り掛かる前ヤナーチェクはノートや紙切れにメモを書き、ベースとなる作品を用いて作品の枠組み(幕やパートの数)を決めました。これは常に予定通りとはいかず、当初の案と出来上がった作品では異なることもありました。オペラのテキストは作曲する前に演劇や小説から修正を加えましたが、テキストの取捨選択や修正を作曲の最中に行うこともありました。
まず草稿を作りました。草稿の裏側には取りやめた個所や作り直した個所がたくさん書かれています。長めの個所(一連の芝居など)を作曲した後には最初の校閲を行いました。これによって例えば最初のバージョンから3分の1の部分がなくなったりしました。ヤナーチェクは話のトーンや全体の意味のために、作曲した個所をばっさり切り捨てることも厭いませんでした。草稿を完成させ校閲も終わった時点で、全体としての見直しを行いました。その後草稿を第一のコピー作成者へと渡しました。第一のコピーはヤナーチェク自身と出版社のために作られました。ヤナーチェクはしばしばコピー完成後にも、特に管弦楽法について手直しを加えました。ヤナーチェクが鉛筆で修正し、コピー作成者がそれをインクで書き直して鉛筆の部分を消しました。この段階で第一のコピーから、初演準備をおこなっている劇場のための第二のコピーができました。第二のコピーの譜表から、オーケストラと合唱のための楽譜が出来上がりました。 ピアノ・リダクション用の楽譜は第一のコピーから作られました。たくさんの変更箇所や修正箇所は最初の上演準備及びそのあとに見つかりました。ヤナーチェクは指揮者とともにディテールにもこだわり、ダイナミックさや管弦楽法を修正しました。変更箇所はそののち自分の(つまり第一の)コピーに、例えばオーケストラのパートに変更箇所の概要がわかるよう赤いインクで記しました。その後ヤナーチェクは楽譜をもう一度チェックし、出版社(オペラの場合はウィーンのユニバーサル・エディション社)に送りました。出版社にはその後もその都度再修正箇所を送りました。故に最終的には第一のコピーと第二のコピー、そして出版社によるバージョンでは内容が違うことがよくありました。出版前の最終チェックにはヤナーチェクはあまり関わらず、たいていすでに次の作品に取り掛かっていたこともあり、自身の生徒たちに任せていました。



執筆:イジー・ザフラートカ「偉大なチェコの作曲家たち」(国立博物館、2020年)より抜粋。